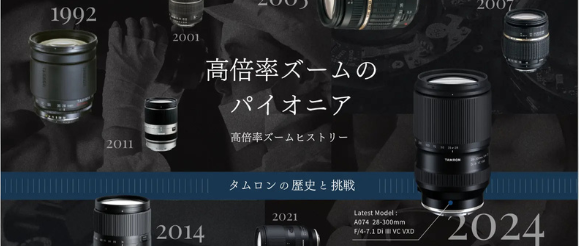2024.09.30
マクロレンズとは?選び方のポイントやおすすめの撮影シーンをご紹介
マクロレンズとは?選び方のポイントやおすすめの撮影シーンをご紹介



接写撮影(マクロ撮影)とは、レンズを被写体に大きく近づけて撮影することを指します。マクロレンズは、通常のレンズではピントが合わなくなるほど、被写体に寄って撮影できる点が特徴です。このため、接写でも高い解像度で、被写体の細部を精細に捉えることができます。

最大撮影倍率とは、最短撮影距離において、被写体の実際の大きさと、カメラのセンサー上に写る像の最大の大きさとの比率を表す数値です。被写体の実際の大きさと、センサー上の像の大きさが同じ(1:1)場合、等倍の撮影倍率となります。
通常、等倍の最大撮影倍率を持ったレンズがマクロレンズ(等倍マクロ)と呼ばれます。また、像の大きさが実際の大きさの半分(1:2)である場合、ハーフマクロレンズ(ハーフマクロ)と呼ばれます。
最短撮影距離とは、被写体にピントが合って見える状態での、被写体とカメラのセンサーまでの間の最も短い距離を指します。また、被写体とレンズの先端までの距離をワーキングディスタンスと呼びます。
マクロレンズは最短撮影距離が短いことが特徴で、焦点距離によってその長さが異なります。
たとえば、中望遠マクロレンズである「90mm F/2.8 Di III MACRO VXD (Model F072)」の最短撮影距離は23cm、ワーキングディスタンスは約8.2cm程度です。
一方、標準マクロレンズの場合、最短撮影距離とワーキングディスタンスはさらに短くなります。昆虫など警戒心の強い被写体を撮影する場合は、ある程度の距離を保つ必要があるため、望遠マクロレンズが適しています。

マクロレンズの最大の魅力は、小さな被写体を大きく捉えられる点です。これにより、肉眼では見えない植物の細かな構造や昆虫の複雑な模様、水滴の美しさなどを精緻に描写し、画面いっぱいに写し撮ることができます。
被写体の細部まで鮮明に捉えられるため、写真を見る人に新たな発見や感動を与えることができるのです。

マクロレンズは一般的に被写界深度が浅く、大きなボケを得やすいという特徴があります。
このボケ味を活かすことで、被写体をより際立たせ、印象派の絵画のような美しい表現を得ることができます。また、見る人の視線をディテールに集中させることにも繋がります。

マクロレンズは単焦点レンズであることが一般的です。そして、描写性能が高いものも多いため、接写撮影だけでなく、シンプルに単焦点レンズとして他の被写体にも応用できます。
たとえば、ポートレートやスナップ撮影では、大きなボケを活かして、主題が引き立った写真を撮影することができます。また、風景写真においては、遠景から近景までを鮮明に捉えられるため、細部まで高解像な描写が得られます。
一般的にレンズは、焦点距離が固定された単焦点レンズと、焦点距離を変えられるズームレンズに分けられます。単焦点レンズは開放F値が小さく明るいレンズが多いため、ボケの大きな写真を撮影しやすいという特徴があります。
マクロレンズは基本的に単焦点レンズが多く、接写時でも明るく精細な描写ができるように設計されています。したがって、マクロレンズは(多くの場合)単焦点レンズの一種ですが、接写性能に特化しているレンズといえるでしょう。
関連記事:レンズの種類と選び方の基礎知識 - 初心者の方におすすめのレンズもご紹介!

一方、ハーフマクロは最大撮影倍率が1:2、つまりセンサー上に映る像の大きさは、実際の被写体の大きさの半分になります。
ハーフマクロは、ディテールに寄りすぎず、ある程度背景も取り込んで撮影するのにも適しているといえるでしょう。

マクロ撮影では、主題がしっかりと強調されるため、日の丸構図や被写体の対称性を活かした構図が効果的です。また、主題と背景ボケの色味のコントラストがあるとメリハリが生まれ、印象的な写真になります。
一方、主題と同色の背景の場合は、ふんわりとした柔らかな雰囲気を演出しやすくなります。同じ被写体でも、背景や構図のバランスで大きく異なる表現ができるのも、マクロレンズの魅力です。
関連記事:【初心者の方必見】上手な写真を撮るための構図・アングルの基本を分かりやすく解説!

マクロレンズを使用すると、草花の葉脈、表面の細胞組織、雄しべや雌しべなど、被写体の細部まで捉えることができます。花が密集する場所では、背景ボケに群生する花を取り入れることで、やわらかな絵画のような写真になります。
一方、一輪の花に着目し、シンプルな背景を選ぶことで、花びらの繊細な質感や花粉の粒子など、より細部に焦点を当てることができます。

昆虫の表面には、肉眼では捉えられない模様や関節、組織、体毛などのディテールがあります。マクロレンズを使用することで、こうした微細な構造を写すことができます。見る人に新たな発見を与えるような写真になるでしょう。
昆虫は警戒心が強いため、被写体とある程度の距離がとれる望遠マクロレンズがおすすめです。遠くから忍耐強く撮影することで、印象的な作品が得られるでしょう。

植物などの表面に付着した水滴は、マクロレンズならではの被写体です。水滴の美しい球面のほか、表面に反射した光や風景まで捉えることができ、幻想的な写真を撮影できます。
一見、単純な被写体ですが、背景の選び方や構図の切り取り方次第で、作品の印象が大きく変わります。様々な表現に挑戦できるのも面白いポイントです。

テーブルフォトでは、主役となる料理や小物にフォーカスしつつ、背景ボケや光の工夫でその場の雰囲気を演出したり、ストーリー性を加えることができます。
標準マクロレンズは椅子に座りながらでも被写体に寄ることができ、食材の質感や食器の細部まで表現できます。

古い家具や道具のディテールから、経年による表面の質感、模様など、細部の雰囲気までも写真に収めることができるのがマクロレンズの魅力です。
お気に入りの雑貨や趣味で集めた小物などの撮影でもマクロレンズが活躍します。たとえば、コレクションとして収集したフィギュアをマクロレンズで撮影することで、被写体の細部やテクスチャーを鮮明に捉え、詳細なディテールや素材がよりリアルに表現されます。また、フィギュアの小さな部分を拡大して撮影することで、面白い構図を見つけたり、作品にストーリー性を持たせることも可能です。

マクロ撮影では、被写体のディテールを高解像に描写しつつ、滑らかなボケ味があることで美しい作品になります。また、とろけるようなボケの中に主題を捉えることは、マクロ撮影の醍醐味、そして楽しみでもあります。
解像性能やボケの質感はレンズによって変わってきます。購入前に、イメージする表現が得られるか、作例写真やレビューなども確認してみると良いでしょう。
タムロン 90mm F2.8 (Model F072) の撮影サンプル(等倍写真)を見る >
開放F値がF2.8以下の小さいレンズは、大きなボケの写真を撮りやすくなります。また、日陰や屋内など、暗所でも露出を確保しやすくなるため、できるだけ開放F値が小さいレンズを選ぶと様々なシーンに対応できるでしょう。
関連記事:F値(絞り値)とは?設定例やシャッタースピード、ISO感度との関係まで徹底解説
マクロレンズでは、中心となる被写体にスムーズかつ正確にピントを合わせる性能が求められますので、AF精度もチェックしておきましょう。
一方で、マクロ撮影ではマニュアルフォーカス(MF)で撮影することも多いため、フォーカスリングの操作性なども確認しておくと良いでしょう。
タムロンのAF技術を詳しく見る >
タムロンのマクロレンズは「タムキュー(タムQ)」の愛称で長年親しまれている90mmマクロのほか、ハーフマクロレンズも多くラインアップしています。軽量・コンパクトで使いやすく、高解像なレンズがタムロンの特徴です。ぜひ、気に入ったレンズを探してみてください。
関連ページ:タムロンの90mmマクロレンズ「タムキューの歴史」
等倍マクロ(1:1)対応レンズ
-

-
90mm F/2.8 Di III MACRO VXD f072(Model )
90mm F/2.8 Di III MACRO VXD (Model F072)は、長年「タムキュー」の愛称で親しまれてきたタムロン90mmマクロレンズのミラーレス版です。高い解像力と光学性能を誇り、タムロン初の12枚羽根の円形絞りが、美しい玉ボケと光芒表現を実現します。軽量・コンパクトなデザインで気軽に持ち運べ、新型の窓付きフードでフィルター操作も容易です。さらに、TAMRON Lens Utility™に対応し、高速・高精度AFを搭載したこのレンズは、写真と動画撮影の可能性をさらに広げます。伝統の描写力と最新技術を融合させた、新たな「タムキュー」の歴史を切り拓く一本です。
ハーフマクロ(1:2)での撮影が可能なレンズ
-

-
50-400mm F/4.5-6.3 Di III VC VXD a067(Model )
50-400mm F/4.5-6.3 Di III VC VXD (Model A067)は、広角端50mm始まりでズーム比8倍、フルサイズミラーレス一眼カメラ対応の超望遠ズームレンズです。50-400mm全域で妥協のない高画質を実現するレンズでありながら、100-400mmクラス同等の小型・軽量サイズを達成。リニアモーターフォーカス機構VXD、手ブレ補正機構VCを搭載し、スポーツや野鳥などの撮影で、被写体の動きに素早くピントを合わせられます。近接撮影能力にも優れ、被写体に存分に近づいたハーフマクロ撮影も可能です。Model A067は、圧倒的な高画質と機動力を兼ね備えた新しい超望遠ズームレンズです。
※50mmから70mmまで最大撮影倍率1:2を達成し、被写体に存分に近づいたハーフマクロ撮影をお楽しみいただけます。
-

-
20mm F/2.8 Di III OSD M1:2 f050(Model )
F/2.8の明るさと高い近接撮影能力を合わせ持つレンズが登場。Model F050は超広角撮影を本格的に楽しめる20mmの単焦点レンズです。最短撮影距離0.11mまで寄れば、未体験の超広角世界を楽しむことができます。
-

-
24mm F/2.8 Di III OSD M1:2 f051(Model )
“驚異的に寄れる”広角単焦点レンズが登場。Model F051は広角写真のバリエーションを広げる焦点距離24mm、最短撮影距離0.12mを実現しています。撮影のフットワークを軽くする小型・軽量設計でスナップに最適なレンズです。
-

-
35mm F/2.8 Di III OSD M1:2 f053(Model )
ミラーレス専用設計のソニーEマウントレンズシリーズに単焦点35mmが登場。Model F053はF/2.8と大口径でありながら最短撮影距離0.15mまでの近接撮影が可能。被写体が引き立つ美しいボケを楽しむことができます。