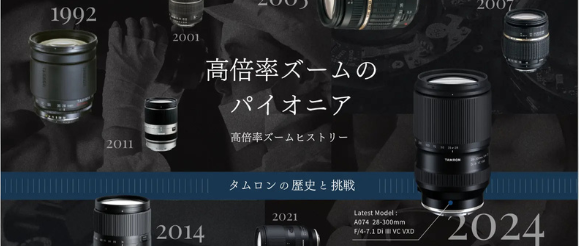2024.12.25
【月の写真の撮り方】月を美しく、魅力的に撮影するコツをご紹介
【月の写真の撮り方】月を美しく、魅力的に撮影するコツをご紹介


スマートフォンでも月の撮影はできる?
はじめに、「スマートフォンでも月は撮影できるのではないか?」という疑問を持つ方もいると思います。スマートフォンのカメラ性能は年々向上しており、設定を工夫したり、専用のアプリを使用することで、月の撮影にも挑戦できます。
しかし、スマートフォンのカメラは一眼カメラと比べてセンサーサイズが小さく、レンズの明るさや望遠能力に限界があるため、どうしても粗くぼやけた写真になってしまいがちです。写真いっぱいに大きく、月の輪郭や表面まで精細に描写するためには、一眼カメラと適したレンズが必要不可欠です。
月の撮影に役立つアイテム
月を美しく撮影するには、望遠レンズが必要です。また、いくつか持っておくと良いアイテムがあります。ここでは、月の撮影に役立つ機材についてご紹介します。
望遠レンズ(超望遠レンズ)
月の撮影には、焦点距離の長い望遠レンズが必要です。焦点距離が約200から300mm程度の望遠レンズ(または300mm以上の超望遠レンズ)であれば、月の表面やクレーターまで捉えることができるでしょう。
ただし、一般的な望遠レンズでは画面いっぱいに月を捉えることができないため、撮影後にトリミング(切り抜き)の作業が必要になります。トリミングせずに画面いっぱいに月を写す場合、焦点距離が約600mm程度以上の超望遠レンズが必要です。
関連記事:望遠レンズとは?使い方やレンズ選びのポイントもご紹介
テレコンバーター
テレコンバーターは、望遠レンズの焦点距離を伸長できるアクセサリーです。前述の通り、画面いっぱいに月を写すためには非常に焦点距離の長いレンズが必要ですが、そうした超望遠レンズは一般に高価で、手軽に利用できないでしょう。
そこで、一般的な望遠レンズや手持ちの超望遠レンズにテレコンバーターを装着することで、焦点距離を伸ばし、より本格的な月の撮影を楽しむことができます。ただし、すべてのカメラとレンズがテレコンバーターと互換性があるわけではありません。また、テレコンバーターを使用すると、レンズの開放F値が大きくなったり、オートフォーカスの速度が遅くなることがあるので、カメラとレンズの仕様を事前に確認し、撮影時には設定を適宜調整することが重要です。
三脚、レリーズ
月の撮影では、カメラのブレを最小限に抑えることが大切です。特に月を大きく写す場合や、シャッタースピードが遅くなる三日月の撮影では、手ブレが生じやすくなります。そのため、三脚を使用すると安定した撮影ができます。
また、シャッターを押す際のブレを抑えるために、ワイヤレスレリーズやケーブルレリーズを使うのも効果的です。もしレリーズを持っていない場合は、カメラのセルフタイマー機能でも代用できます。
一眼カメラ本体の設定
月を美しく撮影するためには、カメラ本体の設定も重要なポイントになります。ここでは、月の撮影に適した一眼カメラの設定について解説します。
関連記事:【一眼カメラの基礎知識】露出や構図など撮り方のポイントを解説
撮影モード
月の撮影では、マニュアルモードを使用しましょう。カメラが自動で露出を決めてくれる絞り優先モード、シャッタースピード優先モードなどを使用すると、月が白飛びしやすくなり露出の調整が難しくなります。
マニュアルモードの撮影に慣れていない方にとっては難しく感じられるかもしれませんが、以下にご紹介するように一般的な値はある程度決まっているため、そちらを参考に設定してみましょう。
F値(絞り値)
一般に夜間の撮影ではF値を小さくしますが、月は十分に明るい被写体なので、レンズの絞り(F値)を開放に近づける必要はありません。むしろ、ある程度絞ったF値(F8からF11程度)で撮影する方が、月の輪郭や表面の模様をよりシャープに描写することができます。ただし、絞りすぎるとシャッタースピードを遅くする必要があり、手ブレが発生しやすくなるため注意が必要です。
関連記事:F値(絞り値)とは?設定例やシャッタースピード、ISO感度との関係まで徹底解説
シャッタースピード
月の撮影では、シャッタースピードも重要な設定の一つです。肉眼ではわかりませんが、月は地球に対して一定の速度で動いており、さらに地球も自転しているため、シャッタースピードが遅すぎると被写体ブレが発生します。
目安としては1/200から1/400秒程度のシャッタースピードに設定すると良いでしょう。ただし、手持ち撮影で手ブレが発生する場合は1/800秒程度など、より速めのシャッタースピードに設定します。もし三脚を使用できる場合は、シャッタースピードを少し遅めに設定しても問題ありません。
ISO感度
ISO感度は、レンズを通った光をデジタルカメラ本体のセンサーがとらえた光の量を表した数値です。月の撮影では、まず低めのISO感度(ISO100から200程度)で撮影することをおすすめします。低いISO感度ではノイズを極力抑えたクリアな写真が撮影できるためです。
ただし、三日月などで光量が少ない場合や、シャッタースピードを速くしたい場合は、ISO感度をやや高め(ISO400から800程度)に設定する必要があります。ISO感度を過剰に高くすると細部のノイズが目立つ場合があるため、低めのISO感度で撮影し、必要に応じて調整するのが良いでしょう。
月の写真を上手に撮るためのコツ
月を魅力的に撮影するためには、いくつかのコツがあります。ここでは、上手に月を撮影するためのポイントを6つご紹介します。
①月齢や方角、月の出・月の入り時刻をチェック
月の見え方は、日々変化していきます。満ち欠けの状態を示す月齢は、月齢表などで確認しておくことが大切です。
また、月の方角や高度も季節によって変化するため、それらの情報を合わせてチェックしておきましょう。たとえばアプリを利用すれば、簡単に月の方角や軌道を確認することができます。事前に月の動きを把握しておくことで、効率的に撮影計画を立てられます。
②撮影ポイントをチェック
月の撮影ポイントを選ぶ際は、目的に合わせて場所を決めることが重要です。満月を撮影するだけであれば、月を遮るものがない限り、場所はそれほど重要ではありません。月は十分に明るいため、周囲の光量が問題になることは少ないでしょう。
一方で、建物や山、自然風景と月を組み合わせて撮影する場合は、事前に撮影ポイントを下見しておくことをおすすめします。実際に現地に行ったり、オンライン地図サービスなどを活用して、月の位置や周囲の環境を確認しておけば、当日のスムーズな撮影につながります。
③撮影時は小さく見えても気にせずに。撮影後にトリミングを
月を撮影する際、手持ちの望遠レンズの焦点距離では十分に大きく捉えきれない場合があります。たとえば、200mmや300mmの望遠レンズでは、画面いっぱいに月を写し込むことは難しいでしょう。
そのような場合の対処として、トリミング(切り抜き)を活用します。撮影後に、写真編集ソフトを使ってトリミング(切り抜き)することで、月を大きく見えるように加工できます。
一見、表面のクレーターや模様がきちんと描写できているか不安になるかもしれませんが、200mmから300mm以上の望遠レンズで適切な設定で撮影してあれば、ある程度トリミングしても十分きれいに写し取れるはずです。
④ホワイトバランス
月の色味は、大気の状態や月の高度、周囲の環境光の影響を受けて、その時々で変化します。もし、好みのイメージがある場合は、カメラのホワイトバランス設定を調整することで、理想の見え方に近づけることができます。
たとえば、暖かみのある月の色を表現したい場合は、ホワイトバランスを「曇天(曇り)」や「日陰」に設定すると良いでしょう。逆に、クールな印象の月を表現したい場合は、「昼光色(蛍光灯)」や「電球」に設定するのがおすすめです。ただし、ホワイトバランスの設定は、撮影後に写真編集ソフトで調整することもできるので、撮影時は「オート」にしておくのも一つの方法です。
⑤背景や構図を工夫する
月を画面いっぱいに捉えた迫力のある写真も魅力的ですが、月を様々な背景と組み合わせることで、表現の幅を広げられます。
たとえば、高い建物と月を一緒に撮影すると映画やSFのような、空想的な雰囲気を演出できます。また、月を山や水面と重ねることで、ドラマチックな印象になるでしょう。さらに、月の位置と背景の建物や風景のバランスを考えて構図を決めることで、より印象的な写真を撮ることができます。
様々な角度や構図を試して、自分ならではの表現を見つけてみてください。
関連記事:【初心者の方必見】上手な写真を撮るための構図・アングルの基本を分かりやすく解説!
シーン別の月の撮り方
月の撮影では、月の満ち欠けや周囲の環境によって撮影方法が異なります。ここでは、シーン別の月の撮り方について詳しく解説します。
満月を大きくクリアに
晴天の夜にはっきりと満月が見える場合は、F値をF8からF10、シャッタースピードを1/100から1/400秒、ISO感度をISO100から200程度に設定してみましょう。
この設定を基本として、撮影した写真を確認しながら微調整を行います。もし月が白飛びする場合は露出を低くするため、シャッタースピードをより速くします。逆に、月が暗くなる場合は、シャッタースピードをより遅くしてみましょう。写真の仕上がりを見ながら、試行錯誤を繰り返すことが大切です。
三日月や半月

三日月や半月は、満月と比べて光量が足りないことがよくあります。そのため、シャッタースピードをやや遅く設定した方が、美しく撮影できる場合が多いです。まずは1/100から1/400秒程度で始めてみて、徐々に遅くしていくと良いでしょう。
また、F値をやや小さめにすることで、明るさを確保することができます。ただし、月の輪郭をよりシャープに写すためには、F4からF6程度に設定することをおすすめします。ISO感度もISO100から200程度から始めてみて、暗ければISO400、ISO800などに調整してみましょう。
三日月や半月を撮影するタイミングとして、マジックアワーやブルーアワーが出る時間帯もおすすめです。空の美しいグラデーションの中で月が幻想的に浮かび上がり、より魅力的な写真に仕上がります。
自然風景や建物との重ね合わせ

月を自然風景や建物と組み合わせて撮影する場合、広角レンズを使用すると効果的です。広角レンズを使えば、手前の風景から遠方の月までを広い画角に収めることができます。
ただし、月は非常に明るいため、夜景や自然風景と合わせて撮影することは難易度が高いです。月が白飛びしたり、周囲の風景が暗くなりやすいのです。
この問題を解決するには、月の出や月の入りのタイミングを狙うのが良いでしょう。月が地平線近くにある時は、月の光が弱く、周囲の自然や建物との明るさのバランスが取りやすくなります。
朧月(おぼろづき)

曇りがかった天候の時は、朧月(おぼろづき)を撮影するチャンスです。朧月とは、雲を通して見える、ぼんやりとした月の姿を指します。この幻想的な月の姿を撮影するには、シャッタースピードをやや遅めに設定します。1から1/100秒程度を目安に、雲の動きや明るさに応じて調整してみましょう。
また、F値をやや小さめにすることで、靄がかった柔らかな光を表現できます。雲が分厚い日は難しいですが、一味違った月の表現を得られるでしょう。
月と星景
月と星空を同時に撮影するには、広角レンズが適しています。広角レンズを使用することで、月と周囲の星空を広い範囲で捉えることができます。ただし、月の明るさが強いため、その他の星とのバランスを取るのが難しい場合があります。
そのため、夜景の撮影と同様に、月の出や月の入りの光が弱いタイミングを狙うのが良いでしょう。
月の撮影に適したレンズの選び方
月の撮影で失敗しないためには、適切なレンズ選びが重要です。ここでは、月の撮影に適したレンズの選ぶ際に、注意しておきたいポイントを解説します。
焦点距離
月を大きく精細に捉えるためには、十分な望遠能力を持ったレンズが必要です。前述の通り、焦点距離が約200mmから300mm程度の望遠レンズであれば、月表面の模様をきちんと描写できます。さらに、300mm以上の超望遠レンズを使えば、より細かなクレーターや凹凸まで写し取ることができるでしょう。
ただし、焦点距離が長くなるほど手ブレが発生しやすくなるため、三脚の使用が不可欠です。また、レンズの重量も増すため、持ち運びや取り回しにも注意が必要です。
関連記事:焦点距離とは?画角との関係など、基礎知識を解説
開放F値
開放F値が小さいレンズほど、より多くの光を取り込むことができます。特に三日月や半月の場合、光量が不足しやすいです。そのような状況でも、開放F値の小さいレンズを使えば、明るい写真を撮りやすくなります。また、開放F値が小さいレンズは、背景をぼかした写真を撮影する際にも効果的なため、月の撮影以外でも幅広く活躍します。
大きさと重さ
望遠レンズは焦点距離が長くなるほど、サイズも大きくなる傾向があります。大きくて重たいレンズは、持ち運びや取り回しに影響するため、実際に手にとって確認をすることがおすすめです。月の撮影では、三脚を使用することが多いですが、軽くてコンパクトなレンズであれば、手持ち撮影の際にも手ブレを抑えやすくなります。
AF (オートフォーカス)や手ブレ補正機構
月の撮影では暗い環境下でピントを合わせる必要があるため、AF (オートフォーカス)の性能が重要です。スムーズにピントが合い、動く被写体にも追従してくれるレンズを選ぶことをおすすめします。
タムロンのAF技術を詳しく見る →
また、手持ち撮影を考慮するなら、手ブレ補正機構が付いたレンズを選ぶと安心です。手ブレ補正機構は、シャッタースピードを遅くした場合にも、手ブレの少ない写真を撮影するのに役立ちます。
タムロンの手ブレ補正技術を詳しく見る →
月の撮影におすすめのタムロンレンズ
ここまで、月の撮影に適したレンズの選び方について解説してきました。最後に、月の撮影におすすめのタムロンレンズをご紹介します。タムロンの望遠レンズ、超望遠レンズは高画質でありながら、軽量・コンパクトで使いやすい点に特徴があります。初めての1本にも、2本目以降にもおすすめです。
-

-
17-28mm F/2.8 Di III RXD a046(Model )
17-28mm F/2.8 Di III RXD (Model A046)は抜群の携帯性と高画質を両立させた、ミラーレス専用設計のソニーEマウント用大口径超広角ズームレンズです。クラス最小・最軽量を達成し、コンパクトで持ち運びしやすいため、街中や旅先の建造物から山岳の写真までさまざまな風景を気軽に撮影することができます。特殊硝材LD (Low Dispersion:異常低分散)レンズやXLD (eXtra Low Dispersion)レンズを贅沢に使用し、色収差を大幅に抑制。コンパクトボディながら優れた光学性能を発揮します。さらに広角端17mmでの最短撮影距離は0.19mと、超広角ならではのパースペクティブを活かした近接撮影も可能です。AF駆動には高速・精密なステッピングモーターユニットRXD (Rapid eXtra-silent stepping Drive)を搭載。加えて、簡易防滴構造や防汚コートを採用するなど、アウトドアシーンでも快適な撮影をサポートします。このレンズがフットワークを軽くさせ、あなたを新たな景色へと連れだします。
-

-
17-50mm F/4 Di III VXD a068(Model )
17-50mm F/4 Di III VXD (Model A068)は、静止画や動画撮影で使用用途の高い焦点距離をカバーした、超広角域17mmから標準域50mmまでをF4通しでカバーする広角ズームレンズです。ズーム全域で高い描写力を達成しており、画面周辺までクリアに描きます。AF駆動には静粛性・俊敏性に優れたリニアモーターフォーカス機構VXD (Voice-coil eXtreme-torque Drive)を採用し、高速・高精度なAFを実現。また、インナーズーム機構の採用により、ズーム時に長さが変化しないため、静止画撮影だけでなく、ジンバルなどに搭載してもバランスがとりやすく、動画撮影にも最適です。さらに、広角端で最短撮影距離0.19m、望遠端で0.3mと近接撮影能力が高く、被写体に思いきり寄れるため、様々な撮影シーンで個性豊かな一枚を撮影することができます。機動力・利便性に長けたこの1本を持ち歩けば、静止画・動画問わず、ダイナミックな風景からスナップ撮影まで、レンズ交換をせずにバリエーション豊かな撮影が可能です。
-

-
20-40mm F/2.8 Di III VXD a062(Model )
20-40mm F/2.8 Di III VXD (Model A062)は、携帯性を徹底的に追求した、新たな大口径標準ズームレンズです。超広角20mmからはじまり、標準域の40mmまでをカバーしながら、クラス最小・最軽量のサイズ感。ズーム全域で美しい写りも実現しており、静止画撮影だけでなく、Vlogなどの動画撮影にも活躍します。静粛性・俊敏性に優れたリニアモーターフォーカス機構VXDを採用し、高速・高精度なAFを実現。静止画・動画問わず気軽に持ち出し撮影を楽しむことができる、今までにない新しい大口径標準ズームレンズです。
-

-
28-75mm F/2.8 Di III VXD G2 a063(Model )
28-75mm F/2.8 Di III VXD G2 (Model A063)は、高い評価を受けた28-75mm F/2.8 Di III RXD (Model A036)から、第2世代「G2」として、さらなる進化を遂げた大口径標準ズームです。高画質・高解像を実現し、AFの高速化と高精度化を達成しました。広角端での最短撮影距離0.18m、最大撮影倍率1:2.7を実現。新デザインの採用により操作性や質感も向上しました。さらに、独自開発した専用ソフトウェアにより、レンズのカスタマイズが可能になりました。
-

-
50-400mm F/4.5-6.3 Di III VC VXD a067(Model )
50-400mm F/4.5-6.3 Di III VC VXD (Model A067)は、広角端50mm始まりでズーム比8倍、フルサイズミラーレス一眼カメラ対応の超望遠ズームレンズです。50-400mm全域で妥協のない高画質を実現するレンズでありながら、100-400mmクラス同等の小型・軽量サイズを達成。リニアモーターフォーカス機構VXD、手ブレ補正機構VCを搭載し、スポーツや野鳥などの撮影で、被写体の動きに素早くピントを合わせられます。近接撮影能力にも優れ、被写体に存分に近づいたハーフマクロ撮影も可能です。Model A067は、圧倒的な高画質と機動力を兼ね備えた新しい超望遠ズームレンズです。
-

-
70-300mm F/4.5-6.3 Di III RXD a047(Model )
70-300mm F/4.5-6.3 Di III RXD (Model A047)は望遠撮影をより多くの方に楽しんでいただくために生まれました。幅広い望遠域をカバーしながらも、軽量・コンパクトサイズを実現。特殊硝材の採用により、色収差をはじめとした諸収差を抑制し、高画像と美しいボケ味が楽しめます。また、AF駆動には静粛性に優れた高速・精密なステッピングモーターユニットRXDを搭載。風景やスポーツ、鉄道、飛行機の他、ポートレートやスナップなど、手持ちで軽快に撮影を楽しみたいシーンでもその力を発揮します。
-

-
150-500mm F/5-6.7 Di III VC VXD a057(Model )
150-500mm F/5-6.7 Di III VC VXD (Model A057)は、望遠側の焦点距離500mmを確保しながら、手持ち撮影も可能な小型化を実現。高画質な描写性能はそのままに、超望遠500mmの世界を手軽にお楽しみいただけます。追従性に優れた高速・高精度AFと、手ブレ補正機構VCの搭載により、超望遠域での手持ち撮影をサポートします。