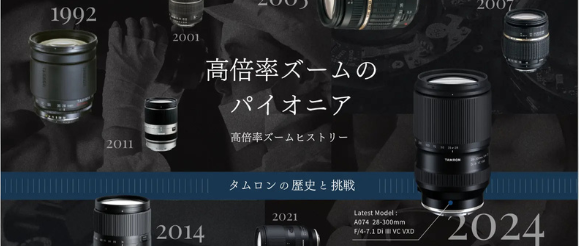2025.03.31
【動画撮影の基礎】カメラワークの基本種類と演出効果を解説!
【動画撮影の基礎】カメラワークの基本種類と演出効果を解説!


カメラワークとは
カメラワークとは、撮影中にカメラの位置や角度を変える技法のことです。静止した映像だけでなく、カメラ自体を動かしたり視点を変えたりすることで、視聴者に様々な印象や感情を与えることができます。
映像制作において、カメラワークは重要な演出要素です。同じ被写体でも、カメラワークの違いによって受ける印象は大きく変わります。たとえば、被写体にゆっくりと近づくことで緊張感を演出したり、俯瞰で撮ることで全体像を把握させることができます。
関連記事:一眼カメラで動画を撮ろう!動画撮影の基礎知識やコツを徹底解説
カメラワークによる効果
カメラワークは単なる撮影技術ではなく、感情や映像の印象を表現する手段です。カメラワークを適切に選ぶことで、伝えたいメッセージをより効果的に届けることができます。ここでは、カメラワークが生み出す効果をおさらいしましょう。
映像にリズムやメリハリを生む
同じカメラワークばかりを使うと映像は単調になりがちです。異なるカメラワークを効果的に使い分けることで、映像に変化やリズム、流れを作り出せます。
たとえば、静と動のコントラストをつけることで、重要なシーンを際立たせることができます。長く静止したカメラでシーンを見せた後、突然カメラが動き出すと、その動きをきっかけに注意が引きつけられ、緊張感が生まれるでしょう。
また、長回しの中でカメラを動かすことで、編集でカットを切り替えなくても、視聴者の視線を自然に誘導できます。たとえば、家族の団らんシーンでテーブルの周りをゆっくり移動しながら全員の表情を捉えれば、カットを変えずとも全員の様子を伝えられるのです。
感情や主題となる被写体の印象を強調する
※以下のシーンはカメラワークにより感情や被写体の印象が強調された一例となります。
カメラワークは、登場人物の感情や主題となる被写体の印象を強調する役割があります。たとえば、上下の動きを用いることで、喜びや落胆といった感情の変化を視覚的に表現できます。良いニュースを受けた瞬間にカメラを下から上へと移動させれば、喜びや高揚感が視覚的に強調されます。逆に、悲しいシーンでカメラを上から下へ移動させれば、落胆感がより印象的に伝わります。
カメラを動かすスピードを変えることで、緊張感や安らぎなど、シーンの雰囲気を演出することもできます。急激な動きは緊張感や焦りを、ゆっくりとした動きは穏やかさを表現するのに効果的です。
カメラワークの種類
カメラワークは大きく分けて、カメラの位置を固定するもの、カメラ自体を動かすもの、レンズの機能を使うものの3種類があります。これらを理解することで、撮影したい場面や表現したい感情に合わせて最適なカメラワークを選べます。
カメラを固定する「フィックス」
フィックスは三脚などでカメラを完全に固定して撮影する最も基本的なカメラワークです。一見シンプルですが、他のカメラワークの土台となる重要な技法です。
フィックスの最大の特徴は、安定感のある映像が得られることです。カメラが固定されているため、被写体の動きや表情の変化を客観的に捉えられます。たとえば風景写真では、カメラが動かないことで風に揺れる木々や流れる雲の動きがより際立って見えるでしょう。
また、フィックスは長時間の撮影や構図を維持したい場合にも適しています。一例として、ドキュメンタリーやインタビュー撮影では、被写体の言葉や表情に集中できるようカメラを固定して撮影することが多いです。
カメラを横に振る「パン(パンニング)」
パンは固定したカメラを水平方向に回転させるカメラワークで、広い風景や動く被写体を追うのに適しています(「横パン」とも呼ばれます)。壮大な山脈の全景や走る犬を追いかけるときなど、静止したカメラでは収まりきらない被写体の撮影に効果的です。
パンを行う際は、横に振るスピードを調整する必要があります。特に望遠レンズを使用している場合は、カメラのわずかな動きでも画面上では大きく移動して見えるため、ゆっくり動かすことが重要です。速すぎると映像がブレて見づらくなる点に注意しましょう。
なめらかな動きを実現するには、三脚の雲台が適切に調整されていること、一定のスピードで操作することがポイントです。動きの始点と終点を決め、その間を一定速度で移動させるイメージです。
パンライトとパンレフト
パンには撮影方向によって「パンライト」と「パンレフト」の2種類があります。それぞれ異なる印象を与えるため、目的に応じた使い分けを意識できると良いでしょう。
パンライトは右方向へのパン撮影で、左から右へと移動する被写体や、右側へと続く風景を捉えるのに適しています。一方、パンレフトは左方向へのパン撮影で、右から左へと移動する被写体や、左側へと広がる景色を撮影するシーンなどで使用されます。
カメラを左右に振る動きで、視点の移動や場面の広がりを伝えたい場合に用いられます。登場人物の動きを追いかけるようにカメラを振ることで、臨場感やスピード感を演出できます。また、広大な風景や街並みを見渡すようにパンを行うと、そのスケール感や空間の広がりを表現できます。さらに、視線を自然に誘導して物語の流れや登場人物同士の関係性を示す場合にも効果的です。
カメラを縦に振る「ティルト」
ティルトは固定したカメラを垂直方向に動かすカメラワークで、高さのある被写体や縦の動きを追うのに適しています(「縦パン」とも呼ばれます)。建物の全景や水の流れなど、縦に長い被写体をダイナミックに見せたい場合に効果的です。また、人物の全身を足元から頭まで見せたい場合などにも使われます。
急激なティルトは映像が見にくくなるため、特に意図がない限り、ゆっくりと一定のスピードで操作することが望ましいです。速すぎると視聴者は映像を追いきれず、不快感を覚えることがあります。意図的に混乱や動揺を表現したい場合を除き、なめらかな動きを心がけましょう。
ティルトアップとティルトダウン
ティルトにも「ティルトアップ」と「ティルトダウン」の2種類があります。それぞれ異なる心理的な効果をもたらすため、表現したいイメージに合わせて使い分けると良いでしょう。
ティルトアップは下から上へカメラを上げる動きで、主題の壮大さや高さを強調したい場合に用いられます。高層ビルを見上げるように撮影すると、その威圧感や圧倒的な存在感を表現できます。また、主人公が成長する様子や、困難を乗り越えて成功する瞬間など、上昇志向や希望を表現したい場合にも効果的です。
ティルトダウンは上から下への動きで、俯瞰からディテールへと視線を導いたり、落下感や終息感を表現したりするのに効果的です。街の全景から特定の建物へと視線を誘導したり、物語の終わりを示唆したりする場面でも使われます。
カメラを移動しながら撮影するカメラワーク
カメラ自体を移動させるカメラワークは、より立体的で臨場感のある映像を作り出します。固定したカメラでは表現できない動きのダイナミズムや空間の広がりを伝えることができます。
本格的な映像を得るためには、スライダーやドリー、ジンバルなどの機材を活用するのが理想的です。これらの機材は、カメラの動きを安定させ、手ブレを抑えます。初心者の方は、まずは手頃な価格のスライダーやジンバルから始めてみると良いでしょう。
主題を追う「トラッキング」
トラッキングは動く被写体と並行して横移動しながら撮影する技法で、人物の歩行や走行シーンでよく使われます。街を歩く主人公に寄り添うように横から撮影したり、走るスポーツ選手を追いかけたりするショットです。ドキュメンタリーやスポーツ映像でもよく活用されています。
被写体との距離を一定に保ちながら動くことで背景が流れ、被写体の動きを強調することが可能です。本格的な映像制作では、レールやスライダー、スタビライザーなどの機材が使用されます。
カメラの寄り引き「ドリーショット」
ドリーは被写体に対して前後に移動するカメラワークで、自然な遠近感が得られます。人物の感情を表現するシーンや、感情的の起伏を強調する場面でよく使われる表現方法です。
主題との距離感の変化により、視聴者の感情移入を促したり、心理的な距離を表現したりできます。たとえば、緊張感が高まるシーンでは被写体にゆっくりと近づき、視聴者の注意を惹きつけることができるでしょう。
本格的なドリーショットにはドリーと呼ばれる台車や専用のレールを使いますが、簡易的にはスライダーやジンバルでも代用可能です。手持ち撮影でもカメラを安定させることができれば、簡易的なドリー効果を出せます。
ドリーインとドリーバック
ドリーインは被写体に近づくカメラワークで、主題への注目を集めたり、緊張感や親密さを表現したりするのに効果的です。ドリーバックは被写体から離れていくカメラワークで、シーンの終わりや別れの場面、状況全体を俯瞰するために用いられます。
ズームと似たカメラワークですが、ドリーはカメラ自体を移動させることで被写体との距離を変えるため、より自然な印象になります。画面内のすべての要素との距離感が変化するため、よりリアルな遠近感が視聴者に伝わるのです。
主題の周囲を回る「サークルショット」
サークルショットは主題を中心に円を描くように回り込むカメラワークで、被写体の存在感を強調できます。また、360度あらゆる角度から被写体を映し出すことで、立体的な印象を与えることができます。映画の重要なシーンやミュージックビデオなどでよく用いられる技法です。また、美術作品やプロダクト紹介など、対象物の全体像を視聴者に伝えたい場合にも効果的です。サークルショットには、円形レールやジンバルを使用します。手持ちでの撮影は難易度が高く、熟練が必要とされます。
レンズによる「ズーム」
ズームはカメラ本体を動かさずに、ズームレンズの焦点距離を変えることで被写体への寄り引きを調整するカメラワークです。カメラを固定したままで被写体を拡大・縮小できるため、初心者でも試しやすいカメラワークといえるでしょう。
一方で、遠近感が伝わりにくく平面的な印象になりやすいという注意点もあります。より臨場感を生み出すにはドリーなど物理的に移動するカメラワークの方が有効でしょう。
ズームインとズームアウト
ズームインは被写体を徐々に大きく映し出す方法で、主題を強調したり、細部へと視線を誘導したりするのに有効です。具体的には、広い風景の中から特定の人物や物に焦点を当てたい場合などです。
ズームアウトは被写体を徐々に小さく映し、周囲の環境や状況全体を徐々に明らかにする効果があります。最初は特定の被写体だけを映し、徐々に引いていくことで、その被写体が置かれている状況や環境を示すことができます。
また、ズームをうまく使うには、ズーム時のスピードも意識しましょう。速度によって、緊張感や時間の経過を表現できます。たとえば、急激なズームはショックや驚きの場面で効果的です。一方、ゆっくりとしたズームは穏やかな感情や緩やかな変化を強調できます。
「アングル」による印象の違い
アングルとはカメラを構える向きや角度のことです。同じ被写体でも撮影する角度によって印象が大きく変わります。たとえば、見上げるように撮影すれば威厳や強さを強調でき、見下ろすように撮影すれば、弱々しい印象や俯瞰での視点を与えることができます。
ローアングルとハイアングル
ローアングルは被写体を下から見上げるように撮影する技法で、主題となる被写体の大きさや存在感を強調して見せる効果があります。たとえば、建物や人物を下から見上げるように撮影すると、その高さや力強さが強調されるでしょう。
一方、ハイアングルは被写体を上から見下ろすアングルです。主題の弱さを強調したり、全体像を俯瞰的に捉える効果があります。たとえば、人物を上から撮影することで小さく、弱々しい印象を強調でき、困難な状況に置かれた登場人物の弱さや無力感を表現するのに効果的です。また、広い場所や大勢の人物を撮影する場合にも、全体を把握しやすいという利点があります。
ダッチアングル
ダッチアングルはカメラを意図的に傾けて撮影する手法で、不安定さや緊張感、混乱した心理状態を表現するのに適しています。水平線が傾くことで見る人に違和感を与え、常軌を逸した状況や危機的な場面を演出できるのです。たとえば、サスペンスやホラー映画などで、主人公が混乱や危険な状況に陥るシーンなど用いられることがあります。
ただし、ダッチアングルは多用すると視聴者が疲れたり、一つ一つの印象が薄れるため、使い所には注意しましょう。映像全体の中での位置づけを考え、効果的に取り入れることで、よりインパクトのある表現が可能になります。
カメラワークの効果を活かす応用技法
基本的なカメラワークをマスターしたら、次はそれらを効果的に活用して、より豊かな表現に挑戦してみましょう。
カメラワークを組み合わせる
パンからティルトへ移行する、ズームしながらドリーするなど、複数のカメラワークを組み合わせることで、より複雑な表現が可能になります。たとえば、パンで風景を見せてから主題にティルトアップすることで、置かれた状況を示しながら、視聴者の目線を自然と誘導できます。また、ドリーインしながらズームアウトすると、被写体を同じ大きさに保ちながら背景の遠近感を変化させるような表現も可能です。
ただし、急激なカメラワークの変化は視聴者を混乱させ、見づらい映像になってしまいます。カメラワークを組み合わせる際には動きの方向性や速度の変化に一貫性を持たせ、視聴者を置き去りにしないように注意しましょう。これには、事前の練習やシミュレーションが必要です。
構図を意識する
カメラワークを行う際も、三分割法などの基本的な構図法を意識することで、バランスの良い映像が得られます。シーンの始まりと終わりの構図をシミュレーションし、スムーズで一貫性のあるフレーミングになるよう心がけましょう。特に編集でカットを繋げる場合には、動きの始点と終点の構図が次のカットと自然につながるよう、プランニングしておくことが重要です。
その他、被写体の進行方向に余白を残すこと(アイルーム)で、動きの方向性や広がりを効果的に表現できます。たとえば、右に向かって走る人物を撮影する場合、その人物を画面の左寄りに配置し右側に余白を残すことで、進行方向への動きを感じさせることができます。このような細やかな工夫が、映像の自然さや見やすさにつながるのです。
関連記事:【初心者の方必見!】上手な写真を撮るための構図・アングルの基本を分かりやすく解説!
複数台のカメラで撮影する
異なるアングルやカメラワークで同時に撮影することで、編集時に表現の幅が広がります。たとえばインタビューシーンでは、正面からのミディアムショットに加えて、横からのアップやワイドショットなど、複数の角度から撮影しておくと話の内容に合わせてカットを選べます。また、一回限りのイベントや再現が難しいシーンでは、複数のカメラで撮影しておくと、確実に必要なショットを押さえられ安心です。
一方、複数のカメラを使用する場合は、色調や露出を統一し、切り替え時の違和感を最小限に抑えるよう心がけましょう。これにより、編集でシーンを切り替えた際にも、色や明るさの違いによる違和感を防げます。
様々な機材を利用する
ジンバルやスライダー、ドローンなどの専用機材を活用することで、プロのようなカメラワークを実現できます。たとえば、ジンバルでなめらかな追従撮影、スライダーで正確な直線移動、ドローンで空撮が可能になります。初心者の方でも、これらの機材を使うことで、一気にプロ感のある映像を作れるでしょう。
一方で、機材に頼りすぎず、シンプルなカメラワークでいかに表現するかを考えることも重要です。高価な機材がなくても、基本的なカメラワークと創意工夫があれば、魅力的な映像を作ることは十分に可能です。むしろ、限られた条件の中で最大限の表現を追求することで、本質的なクリエイティビティが高まることもあります。時には意図的に手持ち撮影の手ブレを活用したり、あえてローテクな手法を選んだりすることで、オリジナリティのある味や雰囲気を生み出すことができるでしょう。
「TAMRON Lens Utility™」を活用する
TAMRON Lens Utilityでは、タムロンのレンズとPCやモバイルを専用のケーブルでつなぐことで、動画撮影に役立つフォーカス操作を含む様々なカスタマイズ機能やレンズのアップデートが行えます。特に、モバイル版では、デジタルフォロフォーカス(DFF)機能により、レンズに触れず、モバイル画面上で簡単に精度の高いフォーカス操作や設定が可能となります。初心者の方にとっては、手動での複雑な操作が難しい場合でも、このようなソフトウェアを活用することで高度な映像づくりが可能になるでしょう。
関連ページ:TAMRON Lens Utility™
動画撮影に適したレンズの選び方
映像制作には適切なレンズ選びも重要です。ここでは、動画撮影に適したレンズの選び方について解説します。
関連記事:ワンランク上の動画を撮るなら一眼カメラ!メリット・おすすめ撮影シーン・交換レンズなどを紹介!
開放F値
F2.8やF4など開放F値が小さいレンズは光を多く取り込めるため、暗い場所でも明るい映像を撮りやすいという大きなメリットがあります。夕暮れ時や室内の自然光だけの環境でも、開放F値の小さいレンズなら、追加の照明なしで美しい映像を撮影しやすくなります。
また、開放F値の小さいレンズでは、大きなボケを活かした映像表現が可能で、主題を背景から切り離して印象的に見せることができます。ポートレートや感情表現の強いシーンでは、特にメリットになるでしょう。
関連記事:F値(絞り値)とは?設定例やシャッタースピード、ISO感度との関係まで徹底解説
焦点距離と画角
広角レンズ(約35mm以下)は空間の広がりを表現でき、狭い場所での撮影や風景、アクションシーンにも適しています。広い画角で撮影できるため、室内や狭い場所でも被写体全体を収めやすく、遠近感が強調されることでダイナミックな映像表現が可能です。
標準レンズ(約50mm前後)は人間の有効視野に近い自然な画角や遠近感が得られるため、日常的なシーンやドキュメンタリーに適しています。ストーリーテリングを重視する動画や、自然な雰囲気を大切にしたいドキュメンタリーなどで重宝するでしょう。
望遠レンズ(約80mm以上)は遠くの被写体を大きく捉えつつ背景との距離感を圧縮する効果があり、ポートレートやインタビューに向いています。被写体と背景の距離感が縮まって見えるため、背景を効果的に活用したダイナミックな構図が作りやすい点も特徴です。また、背景のボケを活かした映像表現にも適しています。
関連記事:画角とは?レンズの使い分けについても知ろう
描写(Look)
描写(Look)とは、映像全体の「見た目」や「雰囲気」、「質感」 を指す言葉です。具体的には、色味(カラーグレーディング)・明暗・コントラスト・シャープさ・トーン など、画面を通じて視聴者が感じ取る映像の世界観や印象を意味します。この描写は、技術的な仕様だけでは判断できないため、実際の映像で確認するのが最も確実です。また、同じメーカーでレンズを揃えることで、統一感のある映像になるでしょう。
フォーカスブリージング
フォーカスブリージングは、フォーカスを変える際に画角が微妙に変化する現象です。特に写真用に設計されたレンズでは、この現象が現れやすいといわれます。写真撮影では問題になりにくいですが、動画撮影ではピントを頻繁に移動させるため、違和感を感じやすいのです。可能であれば実際に試してみるか、レビューやテスト動画などでフォーカスブリージングの程度を確認しておくと安心です。
ズームした際の軸ズレ・ピントズレ
ズームレンズの広角端と望遠端で光軸がズレることを「光軸ズレ」といいます。光軸ズレが大きいと、ズーム操作中に被写体が画面の中心から動いてしまい、不自然な印象を与えることがあります。
また、ズームレンズの焦点距離によってピント位置がズレることを「ピントズレ」といいます。たとえば、広角側でピントを合わせた後、望遠側にズームするとピントがズレてしまう現象です。写真撮影ではその都度ピント合わせをすれば問題ありませんが、動画撮影中のズーム操作では問題となり得ます。
このように、写真用のレンズを使用する際は、ズームの変化によるピントズレの大きさを確認しておきましょう。
タムロンではレンズファームウェアを更新することで、動画や静止画(AF-C使用)の撮影において、ズーミング時のAF性能向上を推進しています。
フォーカスリングなどの操作性
フォーカスリングの抵抗感や滑らかさ、AF/MF切り替えのスムーズさなど、操作のしやすさもチェックしましょう。特にマニュアルフォーカスを多用する場合は、フォーカスリングに適度な抵抗感があり、なめらかに回転するものがおすすめです。また、フォーカスの回転方向が、慣れている方向と合っているかも確認しておくと良いでしょう。
AF/MF切り替えのスムーズさも重要なポイントです。撮影中に頻繁に切り替える場合は、スイッチの位置や操作感、切り替え時の音なども考慮に入れると良いでしょう。
重さ・コンパクトさ
長時間の手持ち撮影では、軽量でコンパクトなレンズだと安定したカメラワークを維持しやすいです。特に、ジンバルなしの手持ち撮影や、長時間のドキュメンタリー撮影などでは、レンズの重量は非常に重要なポイントになるでしょう。
重さだけでなく、取り回しの良いレンズは様々なアングルやポジションから撮影できる点で重宝します。たとえば、旅行先での撮影やVlogなどでは、狭い場所でも素早く撮影できるコンパクトなレンズが使いやすいでしょう。
簡易防滴機構
防滴機構を持ったレンズは水辺などの撮影にも対応しやすく、撮影の幅を広げてくれます。たとえば、海岸での撮影や雨上がりの風景、水の流れるシーンなど、水との接触リスクがある場面で安心して撮影できるでしょう。屋外の撮影では想定外の悪天候に遭遇することもあるため、防滴機構があると安心して持ち出せます。
オートフォーカス(AF)性能
動画撮影では、静かでなめらかなAF駆動を確認しておきましょう。また、動体追従性能はピントをスムーズかつ正確に合わせる上で、重要なポイントです。特に、スポーツや子どもの撮影など、予測不能な動きを捉える場合には、AF性能が高いレンズが使いやすいです。
レンズ内手ブレ補正機構
手持ち撮影時は手ブレが発生しやすいため、手ブレ補正機構があると安定した撮影がしやすくなります。特に望遠レンズや移動しながらの撮影では、手ブレが発生しやすいため有効です。一方、三脚を使うときやパン撮影など、オフにした方が自然な映像になることもあるため、オン/オフ切り替え操作も確認しておきましょう。
動画撮影おすすめのタムロンレンズ
ここでは、動画撮影に適したタムロンレンズをいくつかご紹介します。タムロンのレンズは優れた光学性能と、軽量・コンパクトな使いやすさが特徴です。Vlogから本格的な映像制作まで、様々なシーンで優れた映像を撮影できます。
-

-
17-50mm F/4 Di III VXD a068(Model )
17-50mm F/4 Di III VXD (Model A068)は、静止画や動画撮影で使用用途の高い焦点距離をカバーした、超広角域17mmから標準域50mmまでをF4通しでカバーする広角ズームレンズです。ズーム全域で高い描写力を達成しており、画面周辺までクリアに描きます。AF駆動には静粛性・俊敏性に優れたリニアモーターフォーカス機構VXD (Voice-coil eXtreme-torque Drive)を採用し、高速・高精度なAFを実現。また、インナーズーム機構の採用により、ズーム時に長さが変化しないため、静止画撮影だけでなく、ジンバルなどに搭載してもバランスがとりやすく、動画撮影にも最適です。さらに、広角端で最短撮影距離0.19m、望遠端で0.3mと近接撮影能力が高く、被写体に思いきり寄れるため、様々な撮影シーンで個性豊かな一枚を撮影することができます。機動力・利便性に長けたこの1本を持ち歩けば、静止画・動画問わず、ダイナミックな風景からスナップ撮影まで、レンズ交換をせずにバリエーション豊かな撮影が可能です。
-

-
20-40mm F/2.8 Di III VXD a062(Model )
20-40mm F/2.8 Di III VXD (Model A062)は、携帯性を徹底的に追求した、新たな大口径標準ズームレンズです。超広角20mmからはじまり、標準域の40mmまでをカバーしながら、クラス最小・最軽量のサイズ感。ズーム全域で美しい写りも実現しており、静止画撮影だけでなく、Vlogなどの動画撮影にも活躍します。静粛性・俊敏性に優れたリニアモーターフォーカス機構VXDを採用し、高速・高精度なAFを実現。静止画・動画問わず気軽に持ち出し撮影を楽しむことができる、今までにない新しい大口径標準ズームレンズです。
-

-
28-75mm F/2.8 Di III VXD G2 a063(Model )
28-75mm F/2.8 Di III VXD G2 (Model A063)は、高い評価を受けた28-75mm F/2.8 Di III RXD (Model A036)から、第2世代「G2」として、さらなる進化を遂げた大口径標準ズームです。高画質・高解像を実現し、AFの高速化と高精度化を達成しました。広角端での最短撮影距離0.18m、最大撮影倍率1:2.7を実現。新デザインの採用により操作性や質感も向上しました。さらに、独自開発した専用ソフトウェアにより、レンズのカスタマイズが可能になりました。
-

-
70-180mm F/2.8 Di III VC VXD G2 a065(Model )
70-180mm F/2.8 Di III VC VXD G2 (Model A065)は、市場でご好評をいただいている大口径望遠ズーム「70-180mm F/2.8 Di III VXD (Model A056)」(以下Model A056)からさらなる進化を遂げ、第2世代「G2」モデルとして誕生しました。本機種では、タムロン独自の手ブレ補正機構VC (Vibration Compensation)を新たに搭載。クラス最小・最軽量*の機動力を維持しながら、より安定した撮影が可能です。また、初代Model A056から光学設計を一新し、ズーム全域で妥協のない高画質な写りを実現。広角端の最短撮影距離も初代の0.85mから0.3mへ短縮することに成功しており、非常に短い最短撮影距離による、本レンズならではのユニークな写真表現が楽しめます。*手ブレ補正機構搭載フルサイズミラーレス用大口径F2.8望遠ズームレンズにおいて。(2023年8月現在。タムロン調べ)