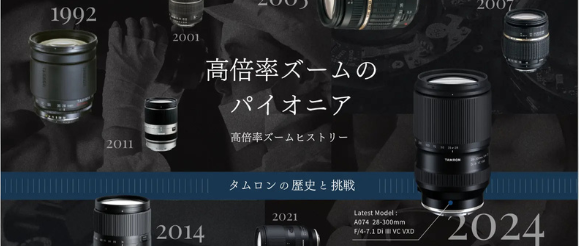2024.05.15
写真家 熊切 大輔氏のスナップ&ドキュメンタリー、1本で撮り切る!28-75mm F2.8 G2 (Model A063)ニコン Z マウント用の幅広い表現力
写真家 熊切 大輔氏のスナップ&ドキュメンタリー、1本で撮り切る!28-75mm F2.8 G2 (Model A063)ニコン Z マウント用の幅広い表現力


私が撮影において最も使える、と思える機能的ポイントはフットワークの良さです。今回使用したタムロン28-75mm F/2.8 Di III VXD G2 (Model A063)ニコン Z マウント用は、最大の特徴としてそのサイズ感があげられます。普段の街スナップでは携帯性も含めて、気軽に日常的に持ち運べることがシャッタ‐チャンスとの出会いを逃さないポイントとなります。一方でやはりその表現力は妥協したくない、キレのある描写力を存分に活かした作品表現を可能にしてくれる、スピード感と描写力を兼ね備えたバランスの良い本レンズで今回の撮影に挑みました。
一枚目の写真 焦点距離:28mm 絞り:F2.8 シャッタースピード:1/25秒 ISO感度:100 使用カメラ:ニコン Z8
サバニは、その美しい流線型の構造が現代のボート開発者も参考にするほどだと言われています。ちょうどこの日は糸満の海開きの日となりました。サバニが滑るように青い海を駆け抜けていく、逆光をあえて選んだ構図ですが、28-75mm F2.8は嫌なフレア・ゴーストもなく日差しを印象的に描いてくれました。
そんなサバニをこよなく愛し、作り続けているのが大城清さんです。しばらくは後継者不足など厳しい時代だったそうですが、最近では若い人、特に女性も興味を示していて、この日も若い女性オーナーが大城さんの元を訪れていました。立体的で程よいレンズのボケ味は、熱く楽しげに語る大城さんの表情をナチュラルに捉えることができました。
三線工房の渡慶次道政さんを訪ねました。ひとつひとつ丁寧に心を込めて作り出す三線。一家にひとつの三線があり代々受け継がれる、沖縄の人々の魂と言っても良いでしょう。吟味された素材から削り出される工程は想像以上の力作業です。鋭い視線でその仕上がりを確認する渡慶次さんの表情を追いました。
三線の持ち手は様々な工具で細かく微調整しながら削り出していきます。繊細で滑らかな曲線を、道具を細かく変えながら生み出しています。鉄ヤスリは一般的な工具ですが、丸みを出すために金槌で打ち出すことでヤスリそのものも丸みを帯びています。近接撮影も特徴の一つである28-75mm F2.8で鋭利な刃の表情を捉えるために、望遠側の最短撮影距離までぐっと寄り、細かいディティールを繊細に写し出すことができました。
次に琉球かすりの大城廣四郎織物工房へ。琉球かすりは沖縄独自の織物でその図柄も特徴的でした。主にそのデザインを担当されている大城一夫さんに染の工房を見せていただきました。かすりといえば藍色を思い出すでしょう。染料の発色良くするために沖縄の酒、泡盛を入れて藍に元気になってもらうという興味深いお話を伺いました。
織り機が所狭しと並ぶ工房からパタンパタンと優しい音が聞こえてきました。ひと織りひと織り心を込めた丁寧な作業が続いていました。写真は経糸を巻き取る作業の様子で、繊細な糸の表情を逆光で捉えてみました。絞り開放で表現されるボケ味もそうですが、解像感も非常に高く、糸一本一本の表情をと捉える描写力は圧巻でした。
海人(うみんちゅ)は沖縄の海の台所、糸満で漁業を行う人を指すと言われています。そこでは漁猟で使う様々なものが生まれました。その代表がミーカガンです。1884年に登場したのは潜水用の水中メガネで現在のそれの原型とされており、糸満市の有形民俗文化財にもなっています。沖縄独自の文化を守るということを、市を上げて取り組まれています。
そんなミーカガンを次の世代へ伝えるべく努力を続ける松田修さん。若い人々たちが制作に関わる事によって、より広い次世代につなげていく、就労支援の形でもミーカガン制作を取り入れることで文化を皆で共有することが大事だと考えられています。後ろにある木材がモンパノキといってミーカガン制作に欠かせない材料であります。