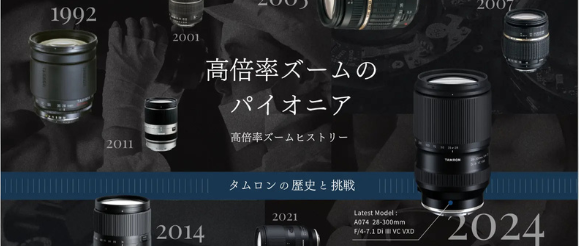2021.05.18
写真家 別所 隆弘氏がTAMRON 70-180mm F2.8 (Model A056)など3本のレンズで撮影する「タムロン大三元 弘前桜紀行」
写真家 別所 隆弘氏がTAMRON 70-180mm F2.8 (Model A056)など3本のレンズで撮影する「タムロン大三元 弘前桜紀行」


今回は、フルサイズミラーレス一眼用の大三元レンズ3本、TAMRON 70-180mm F2.8 Di III VXD(Model A056)、17-28mm F/2.8 Di III RXD (Model A046)、28-75mm F/2.8 Di III RXD(Model A036)を持って、じっくりと弘前の桜を撮影してきました。
状況が状況だけに、撮影に行けるかどうか不安だったのですが、撮影時は青森や私の住んでいる地域にはまだ「まん延防止等重点措置」や「緊急事態宣言」は発出されておらず、感染対策をしっかりした上で撮影することは可能だろうと判断して、弘前に飛び立ちました。ただ、このような状況下にあっては、何よりもソーシャルディスタンスや混雑の回避を心がけなければいけません。そこでまず、三脚などで場所を占有する撮影はやめて、夜景も含めて手持ち&連写で対応しました。混雑しているところには近づかず、必要とあれば、キラーショットも諦めるくらいの想定で撮影計画を立てました。となると、大きな荷物を持ってウロウロはできない。三脚なしだから巨大なレンズでは機動力に欠ける。でも、弘前といえば夜桜や花筏が有名なので、明るいレンズも超広角レンズも欲しい… となった時、今まで散々このブログでもお伝えしてきたタムロンの強みが出てきます。つまり、
1.大口径 F2.8 という明るさの大三元ズームレンズが揃っている
2.大口径大三元なのに、軽くて機動力があり描写に妥協がない
なんとも今回の撮影に都合の良い仕様が盛り込まれている、タムロンの大三元なわけです。というわけで、まずは70-180mm F2.8 (Model A056)の、豪華絢爛、弘前の桜の絶景作例をぜひご覧ください!
一枚目の写真( 焦点距離:180mm 絞り:F/2.8 シャッタースピード:1/8秒 ISO 感度:800 使用レンズ:70-180mm F2.8)
桜の撮影で一番使用頻度の高いレンズって何ですか?超広角マンを自認する私でさえ、実は桜の時期は望遠を持ち出すことが多いのです。その理由は、桜を超広角で撮ると意外とスカスカになるからなんですね。それは弘前のような世界最強の桜を誇る場所でも一緒。むしろあの弘前の強烈な「桜の圧」を出すためには、他の場所以上に望遠が必要だと現地で感じました。今回のキラーショットでも、望遠パワーが遺憾無く発揮されています。
それが最初の一枚です。まさに最強で凄まじい光景。この場所は標準や広角で撮ると、後ろにある桜の存在感が出ないので、まさに望遠撮影の聖地といっても過言ではありません。圧縮効果が最大限に発揮される場所です。さらにこの写真の大事なポイントは、桜を見る人の姿がシルエットで浮かび上がっている点で、とても印象的です。コロナ禍の桜祭りということで、基本的に人流はあまり止まらず、来訪者は写真を数枚撮ると過ぎ去っていきます。自分も今回は三脚を使わず手持ちと連写で撮影しているので、シャッター速度1/8で人がシルエットで残ってくれたのはラッキーでした。いつもだったら、長秒露光で撮るようなシーンですが、70-180mm F2.8の機動力あふれる望遠ズームならではの長所が発揮できた一枚です。ちなみにここでは連写で20枚ほど撮ったのですが、シルエットが綺麗に残ってブレていなかったのがこの一枚です。
立体感を出すために、開放F2.8を活かして手前に大きめのボケた桜を入れました。さらにこの桜は、ほぼ白飛びしているくらいの輝度で手前にあるのでアクセントとして目を引きます。奥の桜に向かって収束していく消失点の「遠さ」を意識させるために大口径のボケを使いましたが、もしボケ自体がうるさいと使いづらい。でもこの70-180mm F2.8なら、絞った時のシャープさと、ボケの美しさが両立しているので、こういうときに最高のパフォーマンスを発揮してくれます。
ボケの使い方は立体感や奥行きを表現できることですが、例えば「解像しすぎないで欲しい部分」をぼかすようにも使えます。F4まで絞って、ピントは真ん中あたりの桜に置きました。実は奥の方で人が写っていますが、その存在感が悪目立ちしない程度にぼやけてくれています。一方手前の桜はきっちりと、そして上品にボケていて、写真全体が質の高い描写で整っている一枚。レンズの素性の良さが際立ちます。
もちろん、ガッチガチに解像して欲しいタイミングでも大丈夫!そこは最新設計のレンズなので高画素カメラの高解像を受け止める性能をきっちりと備えています。順光でガッツリ光の当たった桜と、その後ろに聳え立つ岩木山。この山は弘前から青森にかけてどこからでも見えるのですが、その存在感が遺憾無く描写されています。
さて、70-180mm F2.8の最後の作例は、この暴力的にすら思える色のあふれる桜空間の一枚です。これは望遠ならではというよりも、むしろ「タムロンらしさ」が詰まった一枚。もちろんボディ側との兼ね合いでもありますが、タムロンのレンズといえば、しっかりとした色乗りで、特に僕が好きなのは、青の取り込みです。朝の明るい光を存分に引き受けた青空と、その青の波長を受けた桜のマゼンダ寄りの発色の美しさといったら!!この光景を前にして言葉を失った記憶が、写真の中に刻印されています。
はい、ドーンとまずはこれです。弘前といえば、このお堀が一面ピンクに染まる、散り際の花筏!こういう時、広角があってよかったと心底思う一瞬です。この写真のお堀の右側を少し下ったところにある角から、望遠で圧縮を効かせて花筏を撮った写真はよく見かけるのですが、こんなに豪勢に、堀の端から端まで全部花弁が散っているのを実際に目の前にすると、広角のパースを活かして広大に描写したくなりました。超小型の広角レンズである17-28mm F2.8 (Model A046)は使い勝手も良く、腕を目一杯上に伸ばした体制で撮影しているこの一枚でも、なんなく全貌を綺麗に収めることができました。
広角といえばパースを効かせた表現が魅力ですが、単純に「広い」というのも大事な要素。特にリフレクション撮影の時、上側に広がる桜の枝ぶりと堀に映る様子の上下ともに捉えたいとなると、標準では絶対に追いつきません。ここは望遠で撮っても綺麗だし、標準で撮っても画になりますが、こういうちょっとダイナミックな桜の枝に出会うと、内心ニヤニヤしながら広角をおもむろにカメラバッグから取り出すわけです。すでに撮る前からこの画が見えていました。この豪快な枝ぶり、最高じゃないですか?
写真を始めた頃は広角が苦手でした。その原因は「空」の広角的な広さ。地球上においては今のところ空は「上」にあるので、広角レンズをつけてカメラを上に向けると、どうしても被写体が小さくなってしまい、空が間延びしたように広くなりすぎてしまう。そのアンバランスさに手を焼いたものですが、もしその広々としたブルーバックの空に、桜の花びらが舞ったらどうでしょう。そんなことを思いながら広角をカメラに装着した瞬間、強烈な風が吹きました。
シャッター速度 0.4 秒!?よくこんなの撮れてたなぁと、帰ってデータ見たときに嬉しくなった一枚から。同じ場所の他のカットは全てブレっぶれ。でもたまにこういうのが撮れているのです。現代のカメラの手振れ補正の凄さです。28mmで撮ったこの桜の筏の一枚は、ほとんど見た時の印象そのままの見え方。超広角で強調されるパースもなく、望遠で切り取られる圧縮効果もない、美しい記憶がそのまま残った一枚。28-75mm F2.8の良さは、いつも僕らに寄り添って、こういう一枚を残してくれるところにあります。完璧な解像、完璧な色で。
17-28mm F2.8で撮影した広角の作例の 2 枚目の縦写真で撮った場所と同じところを、28-75mmF2.8で撮った一枚です。時間が違っていて、先の写真は夕方、こちらは早朝。そうなると、見えてくる風景が変わってくるのです。同じ場所でも、手前に浮いている花弁に綺麗に朝の太陽が部分光で当たっている。そこからなだらかに輝度が落ちながら、再び奥の方には朝の太陽がしっかり当たり込んでいるという早朝特有の美しい光のグラデーション。部分だけを見せるのではなく、この雰囲気を見たままに伝えたい時、標準のレンズがチルしてくれます。
今回の記事の最後は、この一枚で。同じ場所から望遠70-180mmで撮った4枚目の写真とぜひ見比べてください。望遠が圧縮効果を使って山の存在感を引き出すとするならば、標準を使って撮るのは、場の空気、その瞬間の記憶、想いです。この写真は、到着してすぐに撮影したものです。噂に聞く「弘前の夜桜」を前に、徐々に暮れなずむ街。お堀の角を曲がった瞬間に目の前に現れた岩木山と、穏やかに暮れる夕焼け空。そして桜。じんわりと胸の内に広がる「弘前に来たんだ」という喜びが、そのまま画になった一枚です。まだなんのレンズを使うかも決めていないままバッグから取り出したカメラには、いつも付いている標準レンズの28-75mm F2.8。そんな「意図しない瞬間」を撮るレンズだからこそ残せる一枚って、確かにあると思うんです。エモでしょ。チルくてエモくて、そんな桜が散る(チルとかけてます!!)時の世界を、「標準レンズ」が全部補完してくれるのです。
今回の撮影で強く思ったのは、今後タムロンの大三元が示すような、機動力、取り回しの良さがカメラ全体の特徴として重視されていくだろうなということでした。我々の社会は、今後コロナをはじめとした新しい感染症と付き合っていかねばならない世界になることが予測されています。そんな中、人混みの中で長時間三脚を構えたり、狭い場所でぎゅうぎゅうになって滞留したりという撮影の仕方は避けなければなりません。今まで以上に、カメラは機動力と即応性が必要になる。そんな状況が予見される中にあって、今回のタムロンの3本のレンズは、見事にこちらの要求に応えて、パーフェクトな結果を残してくれました。ウィズコロナ時代の新しいメインレンズの組み方、使い方として、今回の記事をぜひ参考にしてみてください。
記事で紹介された製品
-

-
17-28mm F/2.8 Di III RXD a046(Model )
17-28mm F/2.8 Di III RXD (Model A046)は抜群の携帯性と高画質を両立させた、ミラーレス専用設計のソニーEマウント用大口径超広角ズームレンズです。クラス最小・最軽量を達成し、コンパクトで持ち運びしやすいため、街中や旅先の建造物から山岳の写真までさまざまな風景を気軽に撮影することができます。 特殊硝材LD (Low Dispersion:異常低分散)レンズやXLD (eXtra Low Dispersion)レンズを贅沢に使用し、色収差を大幅に抑制。コンパクトボディながら優れた光学性能を発揮します。さらに広角端17mmでの最短撮影距離は0.19mと、超広角ならではのパースペクティブを活かした近接撮影も可能です。 AF駆動には高速・精密なステッピングモーターユニットRXD (Rapid eXtra-silent stepping Drive)を搭載。加えて、簡易防滴構造や防汚コートを採用するなど、アウトドアシーンでも快適な撮影をサポートします。このレンズがフットワークを軽くさせ、あなたを新たな景色へと連れだします。
-

-
28-75mm F/2.8 Di III RXD a036(Model )
タムロン28-75mm F/2.8 Di III RXD (Model A036)の製品ページです。フルサイズミラーレス一眼カメラに対応し、小型・軽量と高解像を実現。ミラーレス専用設計のソニーEマウント用の大口径F/2.8標準ズームレンズです。