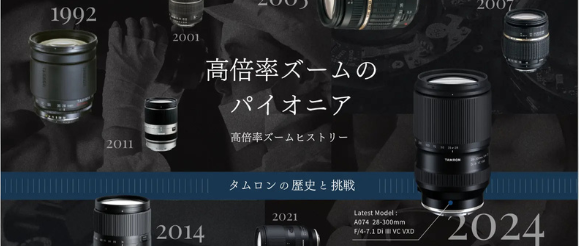2020.07.08
鉄道写真家 杉山 慧氏がフルサイズミラーレス用大口径望遠ズームレンズ タムロン70-180mm F2.8 (Model A056)で鉄道写真を撮る
鉄道写真家 杉山 慧氏がフルサイズミラーレス用大口径望遠ズームレンズ タムロン70-180mm F2.8 (Model A056)で鉄道写真を撮る


鉄道写真家の杉山 慧です。今年も「第2回 タムロン鉄道風景Instagram コンテスト 2020」で審査員を務めさせていただくことになりました。皆様からのご応募をお待ちしております。
さて、ミラーレス専用設計のソニーEマウント用大口径ズームレンズ TAMRON 70-180mm F2.8 Di III VXD(Model A056)がタムロンから登場しました。私はこの焦点距離を鉄道写真でよく使いますが、このレンズは大口径F2.8通しでありながら、質量810gに抑えられています。カメラとあわせても約1460g(α7Ⅲ、バッテリーとメモリーカードの質量を含む)で、フラッグシップモデルの一眼レフカメラ本体と同等の質量なのだから驚きです。
一枚目の写真 焦点距離:180mm 絞り:F/5.6 シャッタースピード:1/2000秒 ISO感度:400
今年3月にデビューした話題の新型近鉄特急「ひのとり」です。艶のある優美な車体に周囲の景色を映しながら名阪間を約2時間で結んでいます。70-180mm F2.8は車体のメタリックレッドを正確に描き出してくれました。このレンズは開放F2.8通しで絞り値の選択肢が多く、幅広い表現ができます。車両の先頭部分と前後数メートルの範囲にピントが合うよう、F5.6で撮影しました。このように望遠で編成写真を撮影する際によく使うF5.6の絞り値で、車両の「顔」を引き立たせる背景の美しいボケ味が得られるのは、F2.8通しレンズならではの「余裕」と言えるでしょう。
「軽いは強い!」これがこのレンズを使ってみた感想です。先述の軽さゆえに、三脚に載せても手持ちでも構図が組みやすく、流し撮りをするときも思い通りに動かせました。もちろん、軽さだけでなく、写り(コントラストや発色)の良さやオートフォーカスなど、鉄道写真における様々な撮影方法を試みました。
はじめに訪れた近畿日本鉄道は、先ほどご紹介した「ひのとり」が登場したことで、特急列車陣営に変化が訪れています。過渡期の鉄道は実に面白いです。個性豊かな特急列車たちを、レンズとカメラの性能を最大限に活かして捉えました。
また、このレンズは軽量かつコンパクトでありながら、大口径望遠ズームで絞り開放値がF2.8通しであることが特徴です。特別企画として別途、小湊鐵道で全ての作例をF2.8で撮影してみましたので、是非最後まで御覧下さい。
「ひのとり」登場で去就が注目される「スナックカー」を撮影しました。標準レンズに近い焦点距離は肉眼での画角に近いため、私の場合、ファインダーを覗かずに「一発撮り」をします。ファインダーを覗かないことで、周囲の状況も視野に入れつつ、緊張せずに撮影できるというメリットがあります。おかげで思い通りのシャッターチャンスで撮影ができました。14群19枚で構成されるこのレンズには高い解像力の得られる特殊硝材が贅沢に使用されていることで、列車先頭部に掲げられた行先表示器の文字や、青空を隅々まで、正確かつ綺麗に写すことができました。
日が傾いた頃、棚田の向こうを駆け上がる「ACE」を半逆光で撮影してみます。BBAR-G2 (Broad-Band Anti-Reflection Generation 2) コーティングが採用されているので、影の部分も真っ黒に潰れずに描き出してくれました。可能な限りローアングルで撮影するために、三脚の脚にクランプ(棒状や板状の部材を挟み込んで固定し、雲台を取付けることの出来る器具)と自由雲台をつけて、小型な機材であることを活かしてガードレールの下の僅かな隙間からレンズを線路に向けます。軽いレンズなので自由雲台の操作も簡単で、すぐに思い通りの構図を組めました。
新型特急「ひのとり」が登場するまでの30年以上、フラッグシップとして名阪間を日夜駆け抜けてきた「アーバンライナー」。残照に浮かぶ白いボディを捉えようと、開けた水田地帯から流し撮りを試みます。斜め前から撮影するため、列車が近づくにつれてカメラを振る速さを上げていかなければなりません。しかも最高速度130km/hで走る列車を至近距離から捉えるので至難の業ですが、ここでもレンズの軽さに助けられ、思い通りの写真を撮影することができました。
上記までの作例は全てマニュアル(MF)でピントを合わせていましたが、ここでタムロン初搭載のリニアモーターフォーカス機構「VXD (Voice-coil eXtreme-torque Drive)」によるオートフォーカス(AF)を試してみます。まずは列車が正面を向く構図です。被写体に選んだ「しまかぜ」はガラスが大きく、どのタイミングなら架線柱などの障害物が写り込まないか、列車が来てみないとわかりません。要するに事前にMFでピントを合わせることができないので、信頼できるAFが必要になるわけです。AF-Cに設定の上、フォーカスエリアをフレキシブルスポットで列車の鼻先にセット。「VXD」によるAFは音もなく一瞬でピントをあわせてくれ、前後のカットも正確にピントが合っていました。
先ほどは正面がちの構図でAFを試してみました。リニアモーターフォーカス機構「VXD」の素晴しさがわかったので、今度は横方向の動きが大きい構図で試してみます。レンズによってはAFが苦手とするシチュエーションです。ここではAF-Cのまま、フォーカスエリアを画面右側の広い範囲に合う「ゾーン」に設定しました。「伊勢志摩ライナー」がフォーカスエリアに入った瞬間に連写を開始、ここでも全てのカットにピントが合ったので、思い通りの撮影ができました。「VXD」によるAF駆動システムが静粛で俊敏、そして何よりも正確なピントを合わせてくれるものだと実感できました。
夕暮れの駅を通過するシーンを捉えます。1.5倍の焦点距離イメージが得られるAPS-Cモードに設定することで、270mm相当の画角で撮影ができました。絞りの開放値がF2.8の通しなので、夕方の薄暗い時間でも明るく、シャッター速度をあげることができ、重宝します。立ち位置が狭く三脚が立てられないので、手持ちで撮影します。望遠いっぱいでさらにAPS-Cモードなので、ちょっとしたズレで構図が大きく変わってしまうのですが、このレンズは軽量なので、手持ちでも安定した構図をキープでき、撮影ができました。
大阪と奈良を結ぶ奈良線。石切駅付近では眼下に大阪平野を望めます。ここはF2.8の美しいボケ味を活かして、絞りを開放にして大阪の夜景をボカし、低速シャッターで列車の動感を出します。家路につく人々を乗せた「ビスタカー」が生駒山地へと駆け上がっていきます。F2.8であるからこそ得られた、ボケ味の美しい写真に仕上げることができました。
小さな踏切の傍に、見事なアジサイが咲いているのを見つけました。しっとりとした天気が良く似合います。アジサイにピントが合う範囲や背後の列車のボケ方を考慮してF8で撮影しました。AFである程度ピントを合わせたあと、必要に応じてMFで微調整するダイレクトマニュアルフォーカス(DMF)を試しました。右下手前の花にフォーカスエリアを設定しAFで合わせ、MFで微調整します。このような場面でDMFがしっかり機能しました。
小湊鐵道へ舞台を移し、以下4点の作品は全て開放F2.8で撮影しました。まずは上総鶴舞駅を発車する列車を狙います。APS-Cモードを使った270mm相当の画角です。シビアなピントが求められるF2.8での撮影ですが、リニアモーターフォーカス機構「VXD」によるAFは寸分の狂いもなく、西日を浴びた列車の顔にピントを合わせてくれました。線路まで緑に覆われた南国ムードの溢れる背景も、綺麗にボケるからこそ、その雰囲気が伝わります。
このレンズの魅力のひとつにズーム全域において最短撮影距離が0.85mであることが挙げられます。作例はおよそ0.85mの距離から撮影しました。最短撮影距離が短いということは、被写体から離れなくて済み、より自由な立ち位置や構図で撮影ができます。作例の高滝駅は大正時代に駅舎が作られました。全景を撮っても、一部を切り取っても画になりますが、私は庇を支えるカールのついた支柱に、大正建築ならではの繊細さを感じることができ気に入りました。F2.8で撮るからこそ、見せたい部分を強調できます。
F2.8は前ボケを活かした風景カットでも有効です。ピントを画面の奥にあわせ、手前をボカすことで、目線は自然と奥へと流れていきます。降り続く雨の中、鬱蒼とした森の向こうから列車が現れました。木の葉の1枚1枚の色の違いや、列車から滴る雨粒といった、空気感までも捉えることができました。
このレンズはズーム全域で最短撮影距離が0.85mまで寄れるので表現の幅が広がります。作例もおよそ0.85mまで近接し、開放F2.8で撮影をしました。背景を劇的にボカした印象的な写真となりました。構内踏切のある上総牛久駅、警報器が列車の出発を告げます。柔らかく光る矢印や、何度も塗り直されたであろうペンキの痕跡も捉えてくれます。乗客の後ろ姿が良いアクセントになりました。
今回、近鉄特急と小湊鐵道を撮影したTAMRON 70-180mm F/2.8 Di III VXD (Model A056)。一番の強みである軽量でコンパクトなレンズであることを実感できました。構図の組みやすさや、流し撮りのしやすさなど、気持ちよい使い心地でした。使いやすさだけでなく、写真の仕上がりも見事で、正確な発色をしてくれるのはもちろん、フルサイズカメラの醍醐味であるボケ味も、大口径望遠ズームでF2.8通しを実現しているからこそ思う存分楽しめました。私はこれほどF2.8に拘って撮影したことが過去にありませんでしたが、このレンズが持つ美しいボケ味に出会えたことで今後は積極的にF2.8を使いたいと思いました。タムロン初搭載のリニアモーターフォーカス機構「VXD」によるAFは俊敏かつ正確な信頼度の高いもので、咄嗟の撮影や、連写の際に様々なシャッターチャンスでピントを合わせたいときも安心して使えました。静粛性も見事でAFの動作音を思い出せないくらい、静かに動いてくれました。軽いので、他のタムロンレンズをたくさん持って行っても気持ちよく撮影ができそうです。

Satoru Sugiyama 杉山 慧
1992年静岡県生まれ。日本大学芸術学部写真学科を卒業後、ネコ・パブリッシング「レイル・マガジン」編集部で、編集経験を積んだのち、鉄道写真事務所レイルマンフォトオフィスに入社。同社を2018年に独立した後は、編集・カメラマン経験を活かし、写真撮影のみならず文章の執筆も一手に引き受ける「二刀流カメラマン」として活躍中。2019年には初の個展となる「走れ! グリーンストライプ! 特急『踊り子』号」写真展を開催。 【写真撮影/本文執筆記事】 ・「鉄道ジャーナル644号」三世代が走る伊豆の『踊り子』 Saphir ODORIKO E261,E257,185(鉄道ジャーナル社) ・「鉄道写真の奥義(Motor Magazine Mook)」珠玉の絶景 鉄道撮影地ガイド50選(モーターマガジン社) ・「お立ち台通信vol.22」メインライン/東海道本線 撮影地ガイド(ネコ・パブリッシング) ほか多数